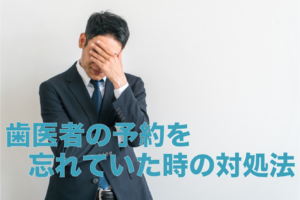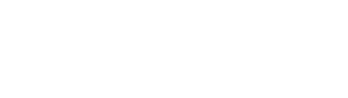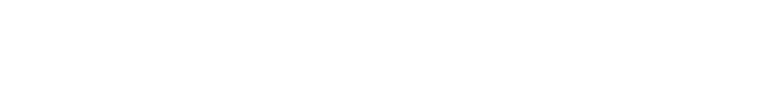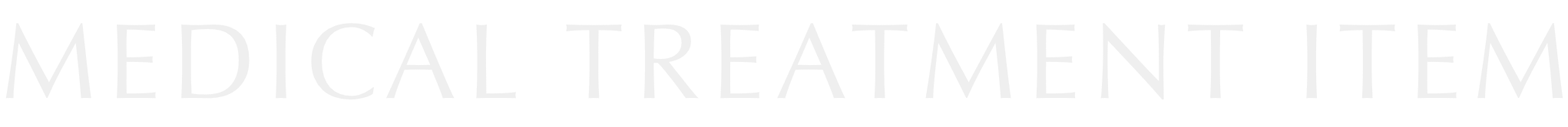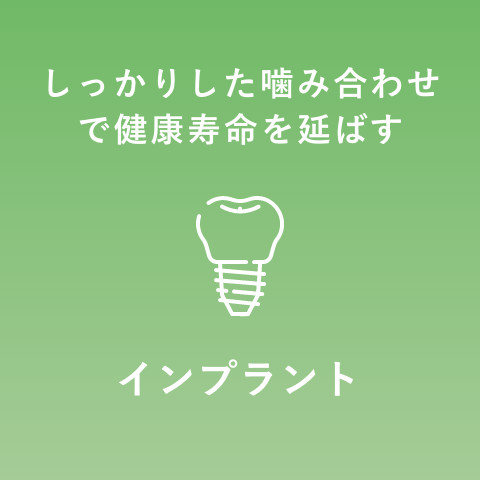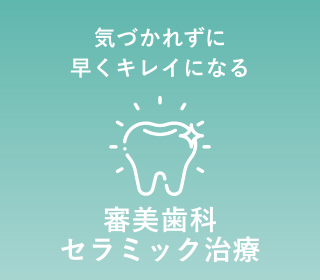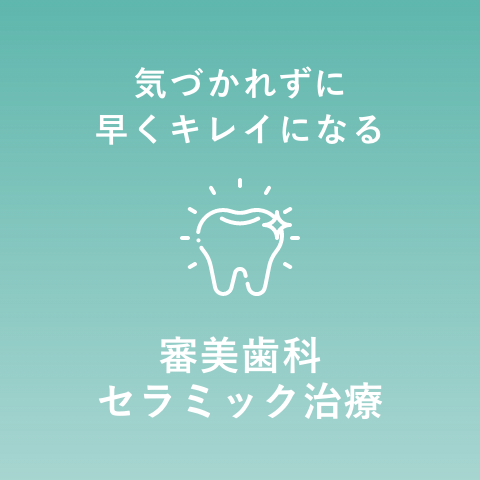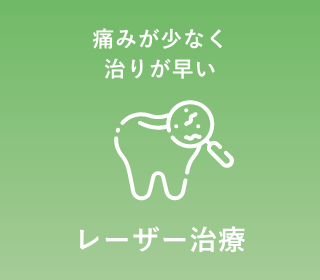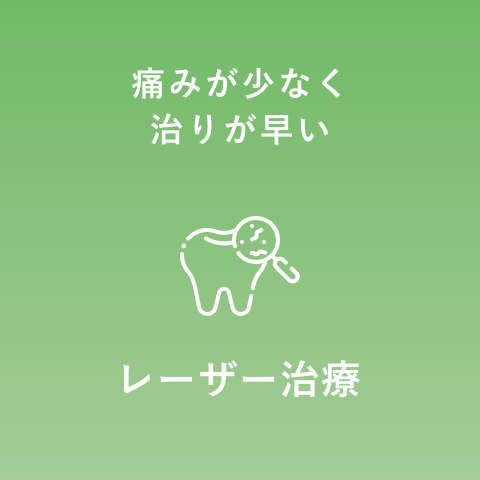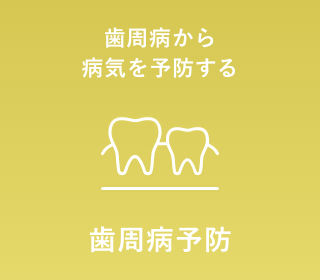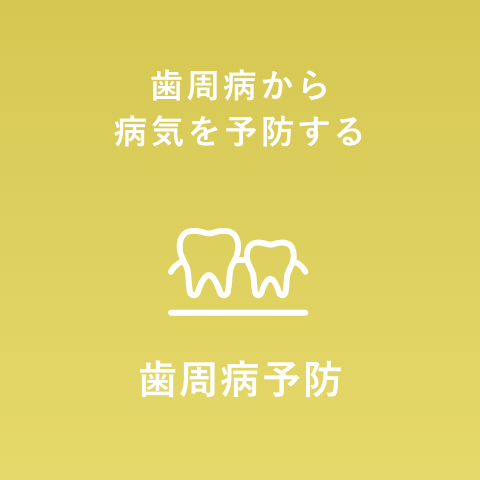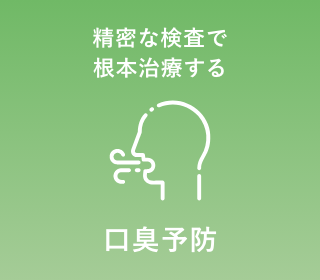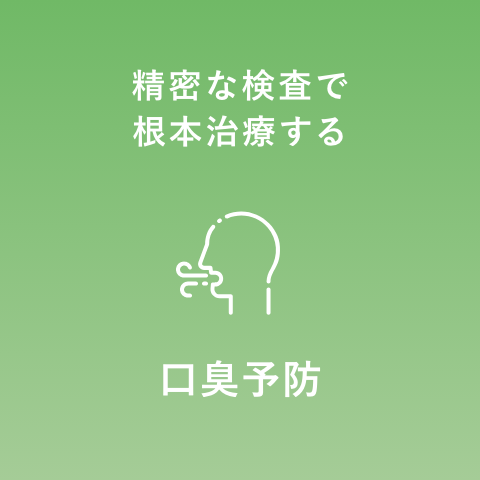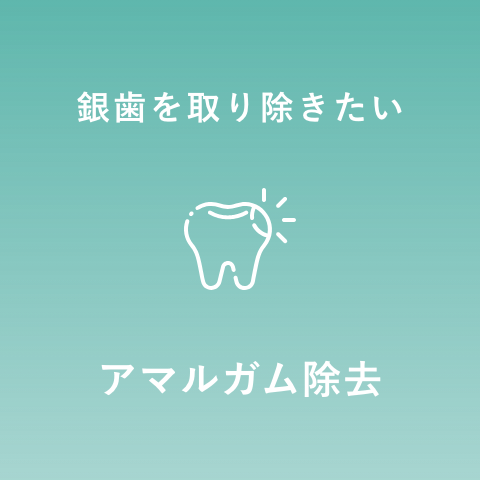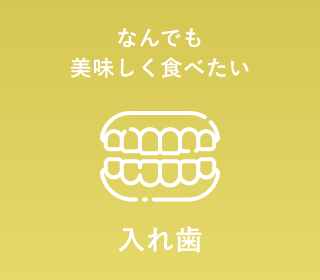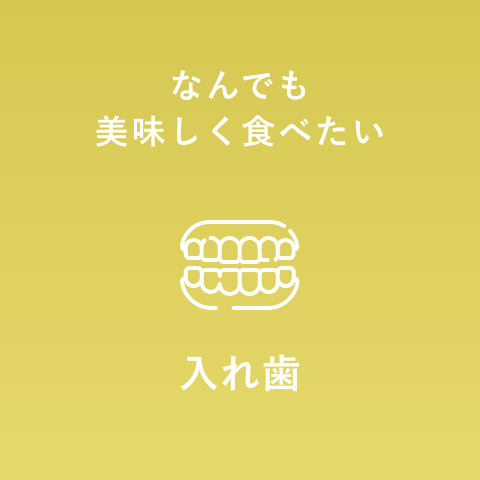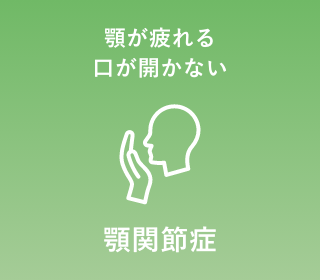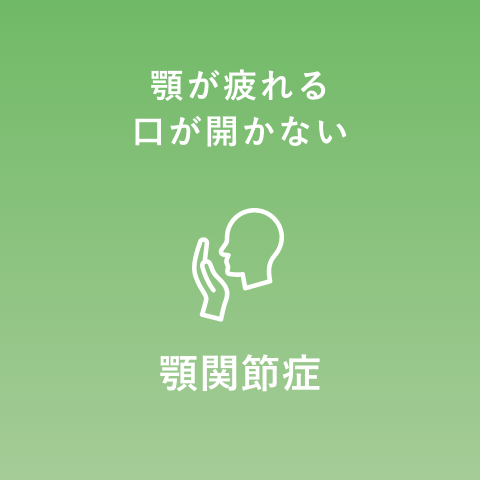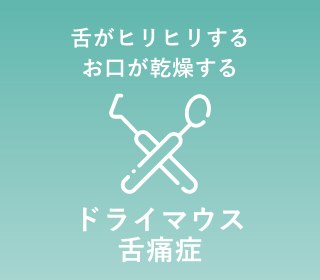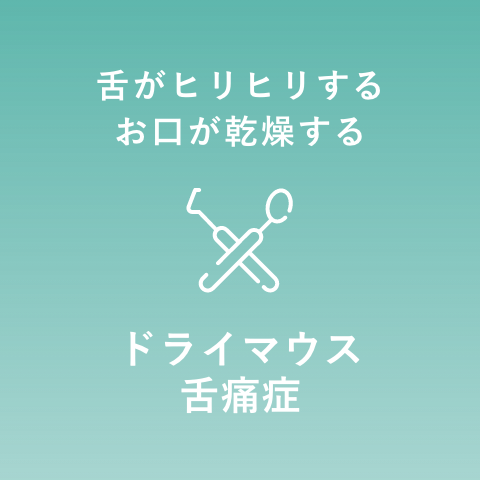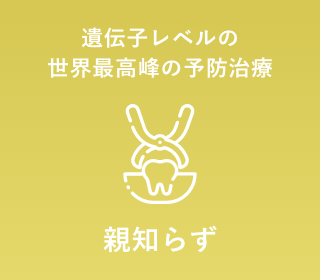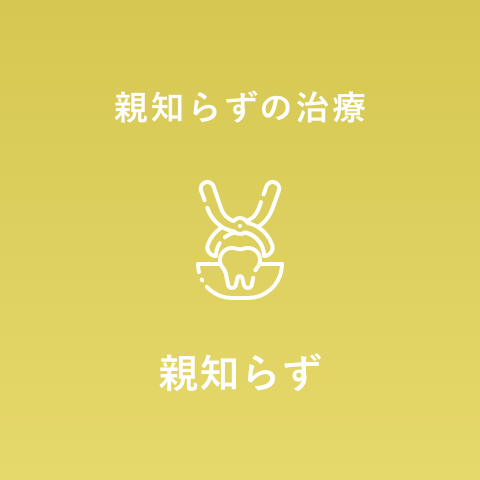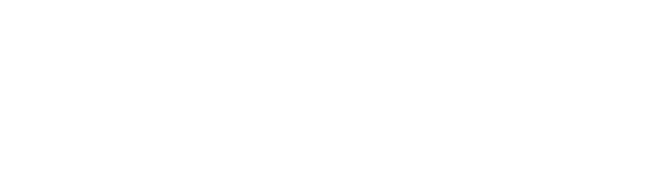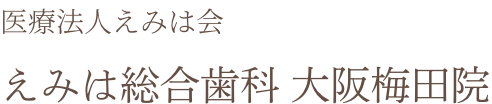歯ぐきの腫れ・出血を放置していませんか?歯周病の初期段階で受ける“THP”治療とは

こんにちは。大阪市北区梅田にある「えみは総合歯科大阪梅田院」です。
歯ぐきからの出血や腫れが気になることはありませんか?
歯周病は自覚症状が少なく、気づいたときには進行しているケースも珍しくありません。
実は、日本人が歯を失う原因の第1位は歯周病です。
当院では、早期発見と予防に注力し、「THP(トータルヘルスプログラム)」という削らず・痛みの少ない予防型のケアを導入しています。
この記事では、歯周病の初期サインや、THPによる当院の取り組みをご紹介します。
目次
歯周病は「沈黙の病気」──気づかないまま進行する恐ろしさ

自覚症状が出にくい歯周病は“気づいたときには手遅れ”も
歯周病は初期にはほとんど痛みがなく、虫歯のように明確なサインが出にくいため、進行に気づきにくい病気です。歯ぐきの腫れや歯みがき時の出血があっても、「たまたまかな」と見過ごされがちです。
しかし、炎症は静かに歯ぐきの奥へ進行し、やがて歯を支える骨を溶かしてしまいます。自覚症状が出るころには、歯ぐきの後退や歯のグラつきなど、深刻な状態になっていることもあります。
成人の約8割が歯周病予備軍。放置すれば進行リスクは高まる
厚生労働省の調査によると、日本の成人の約8割が歯周病またはその予備軍とされています。年齢を問わず、多くの人が歯ぐきに何らかのトラブルを抱えている状態です。
特に40代以降では、「歯は痛くないのに歯ぐきが下がってきた」「歯が長くなった気がする」といった違和感が現れやすくなります。
この段階で適切なケアを行えば進行を防げますが、放置すると歯周ポケットが深くなり、歯槽骨が徐々に破壊されていきます。
歯を失う最大の原因は虫歯ではなく“歯周病”
「歯が抜ける」と聞くと虫歯を連想しがちですが、実際には歯を失う最大の原因は歯周病です。特に中高年以降では、歯を失うケースの多くが歯周病によるものといわれています。
進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、最終的に自然脱落や抜歯が必要になることもあります。
さらに、周囲の歯にまで影響し、複数本を失うリスクもあります。
歯を失えば噛む力が低下し、食事や発音、見た目にも影響が及びます。
歯周病は「口の病気」にとどまらず、全身の健康にも関係する重要な疾患です。
自覚症状がなくても進行していることがあるため、専門的なチェックを受けることが大切です。
歯ぐきが下がる、口臭、歯のぐらつき…進行後のサインに注意
歯周病が中~重度に進行すると、明確なサインが現れます。
代表的なのが、歯ぐきの退縮です。
歯が長く見えたり、歯と歯の間にすき間ができたりします。
さらに、歯を支える骨が溶けると、噛んだときや指で押したときに歯がグラつくことがあります。
また、歯周病菌は強いにおいを出すため、口臭が気になることもあります。
朝起きたときや会話中に違和感を覚えたら、進行している可能性があります。
こうしたサインが出る段階では、元の状態に戻すのが難しくなっているケースもあります。
こんな症状はありませんか?歯周病の初期サイン

歯ぐきが赤い、腫れている
健康な歯ぐきは淡いピンク色で引き締まっていますが、赤く腫れている場合は炎症のサインです。
原因は、歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(細菌)です。
細菌が出す毒素が血流に影響し、腫れや出血を引き起こします。
初期は痛みが少なく、一時的に腫れが引くと「治った」と勘違いしやすい点にも注意が必要です。
とくに奥歯や歯間は見落とされがちなので、「いつもと違う」と感じたら早めの受診をおすすめします。
歯みがき時に出血する
歯みがき中に血が出ると、「強くみがきすぎたかも」と思われるかもしれません。
たしかに力の入れすぎが原因の場合もありますが、頻繁に出血するなら、歯ぐきの炎症が疑われます。
初期の歯周病では、プラークや歯石が原因で腫れやすくなり、軽い刺激でも出血します。
歯と歯の間や境目はとくに注意が必要です。出血を放置すると、炎症が進行し歯周ポケットが深くなることもあります。
気になる場合は自己判断せず、歯科での確認とケアをおすすめします。
口臭が強くなった
「最近、口のにおいが気になる」「家族に指摘された」
そんなときは、歯周病が原因かもしれません。
歯周病が進行すると、歯周ポケット内で細菌が増殖し、不快なにおいのガスを発生させます。
とくに朝や会話のあとなど、においを感じやすくなります。
出血や膿が混じると、においはさらに強くなる傾向があります。
一時的にマウスウォッシュで抑えることはできますが、根本的な改善には歯周病の治療が必要です。
口臭は相談しにくい悩みですが、歯科での診断とケアにより改善が期待できます。
朝起きたとき口の中がネバつく
朝起きたときに「口の中がネバネバする」「乾いている」と感じることはありませんか?
それは歯周病のサインかもしれません。
睡眠中は唾液が減るため、細菌が繁殖しやすくなります。
歯周病があると、歯周ポケット内で細菌が活発になり、ネバつきや不快な味の原因物質を出します。
これは単なる乾燥ではなく、細菌バランスの乱れを示しており、バイオフィルムが残っていると口臭やネバつきが慢性化することもあるため、強いネバつきを感じる場合、すでに歯周病が進行している可能性があります。
初期の歯周病に効果的な「THP治療」とは?

THP(トータル・ヘルス・プログラム)とは
THPは「トータル・ヘルス・プログラム(Total Health Program)」の略で、口腔の健康を全身の健康と結びつけてとらえる、予防重視のプログラムです。
症状が出てからの治療ではなく、生活習慣やリスク因子に早期から介入し、進行を抑えることを目的としており、検査・分析・説明・生活支援を組み合わせたアプローチで、初期段階の歯周病や再発リスクがある方に個別に対応しています。
継続的な改善を目指すこの仕組みは、予防歯科の基盤として注目されています。
「治療」ではなく「予防強化+生活改善」に重きを置く
THPは、外科処置や薬ではなく、日々の口腔ケアや生活習慣の見直しを重視した“予防強化型”のアプローチです。
とくに重要なのは、患者自身が自分のリスクや口腔内の状態を正しく把握すること。
唾液検査や口腔内写真などでプラークの状態やリスク因子(食生活・喫煙など)を可視化し、セルフケア意識の向上につなげます。
THPでは、歯ぐきの状態だけでなく、睡眠やストレス、食習慣など生活全体に目を向け、無理なく改善できるよう支援していきます。
歯科衛生士が中心となって支える継続的プログラム
THPの中心的な担い手は、歯科医師ではなく歯科衛生士です。
患者との面談や検査、プラークコントロールの指導などを通じて、継続的な支援を行います。
とくに歯周病はセルフケアの質が治療結果に直結するため、「一時的な改善」ではなく「継続的な変化」を重視しています。
衛生士が1対1で向き合い、生活習慣の改善や意識の変化を長期的に支えていく体制が特徴です。
定期的な評価と丁寧なフィードバックが、モチベーションの維持にもつながります。
THPはなぜ注目されている?特徴と流れを解説

従来の「削る・抜く」から「守る・育てる」歯科医療へ
以前は、虫歯や歯周病が進んでから「削る・抜く」といった“対処型”の治療が一般的でした。
現在は、病気の予防と歯の保存を重視する“予防型”の医療へと変化しています。
この中で注目されているのがTHP(トータル・ヘルス・プログラム)です。
生活習慣や細菌環境を整え、再発リスクまで見据えた「根本的な予防」を重視します。
口腔と全身のつながりを意識した継続的ケアが、これからの“守る医療”の形です。
THPの基本ステップと“見える化”の工夫
THPでは、口腔内リスクを正確に把握するための「検査」と「見える化」が重要です。
初回のカウンセリングでは、生活習慣やブラッシングの癖などをヒアリングし、唾液検査や口腔内写真、顕微鏡による細菌チェックなどを行います。
これらの情報を可視化することで、患者自身が自分の状態を理解しやすくなり、ケアへの意識づけにもつながります。
なかでも口腔内写真や細菌画像の提示は、現状を具体的に把握するうえで効果的です。
衛生士の継続支援と生活習慣の変化
THPの特長のひとつが、歯科衛生士による中長期的なサポート体制です。
検査や指導を一度で終わらせず、患者様ごとの生活リズムや状況に合わせて、段階的にケアを進めていきます。
歯周病は喫煙・食生活・ストレス・ブラッシングの癖など、生活習慣が大きく関係しています。
衛生士は、それぞれに無理のない改善策を提案し、日常に取り入れやすい形で支援します。
こうした継続的な関わりが、意識の変化や再発予防にもつながります。
こんな方におすすめ
THPは、「まだ重度ではないが気になる症状がある」という方に適した予防プログラムです。
歯ぐきからの出血、口臭、歯が長くなったように感じるなど、初期サインに心当たりがある方は、一度検査を受けてみることをおすすめします。
また、忙しくて定期通院が難しい方や、過去に歯周病と診断された経験がある方にも向いています。
さらに、糖尿病や高血圧などの持病をお持ちの方も、歯周病との関連性が指摘されているため、THPによって口腔内のリスクをコントロールすることが全身の健康管理にもつながります。
えみは総合歯科大阪梅田院におけるTHPの取り組み

全国の歯科50院のみ認可されている厚労省認可のTHP実施クリニック
えみは総合歯科大阪梅田院では、全国に歯科医院が68,000医院ある中、わずか50院程度しか実施できない「THP(トータルヘルスプログラム)」に厚生労働省の認可を受けて取り組んでいます。
THPは、歯周病を「起きてから治す」のではなく、「起こさない」ための根本的な予防治療です。
従来は難しかった虫歯菌や歯周病菌の個別特定を、遺伝子レベルで分析できるのが大きな特長です。
THPはすでに世界各地で導入されており、アメリカ歯周病学会では国際的な予防基準として認定されています。
日本国内ではごく限られた歯科医院でのみ提供されており、当院はその数少ない認定施設のひとつです。
歯ぐきと全身をつなぐ「根本的な歯周病治療」
THPでは、遺伝子検査により口腔内の病原菌の種類や割合を把握し、細菌バランスを整えて虫歯や歯周病になりにくい環境をめざします。
なかでも慢性歯周病と関係の深い「PG菌」は、通常の顕微鏡では見つかりにくい菌ですが、当院の検査では検出と管理が可能です。
このような細菌レベルでの分析は、お口だけでなく全身疾患の予防にもつながります。
THPは、口腔から全身の健康を支える取り組みです。
精密な検査とデータに基づいたプログラム設計
当院ではTHPにおいて、以下4つの精密検査を実施しています。
- 遺伝子検査:歯周病の原因菌を特定
- ガスクロマトグラフ:細菌の種類や数、内臓由来の揮発性成分などを分析
- 位相差顕微鏡検査:口腔内の細菌の動態を可視化
- 唾液検査:分泌量や性質から粘膜や細胞の状態を評価
これらの検査を組み合わせることで、歯周病や虫歯の発生要因をより正確に把握し、患者様に合わせた最適な予防計画を立てることが可能になります。
痛みを抑えたレーザー治療も併用
THPの補助的な治療として、当院では最新のレーザー治療機器も導入しています。
歯周ポケット内の細菌を殺菌・洗浄することで、歯ぐきの腫れや出血を抑え、治癒のスピードを高めることができます。
レーザーは痛みや刺激が少なく、副作用も少ないため、従来の歯周病治療に比べて患者様の負担を軽減できる点もメリットのひとつです。
「見えない歯周病菌へのアプローチ」と「見える範囲での物理的ケア」の両面から治療を支えることで、より効果的な歯周病対策が可能になります。
歯周病とTHPに関するよくある質問
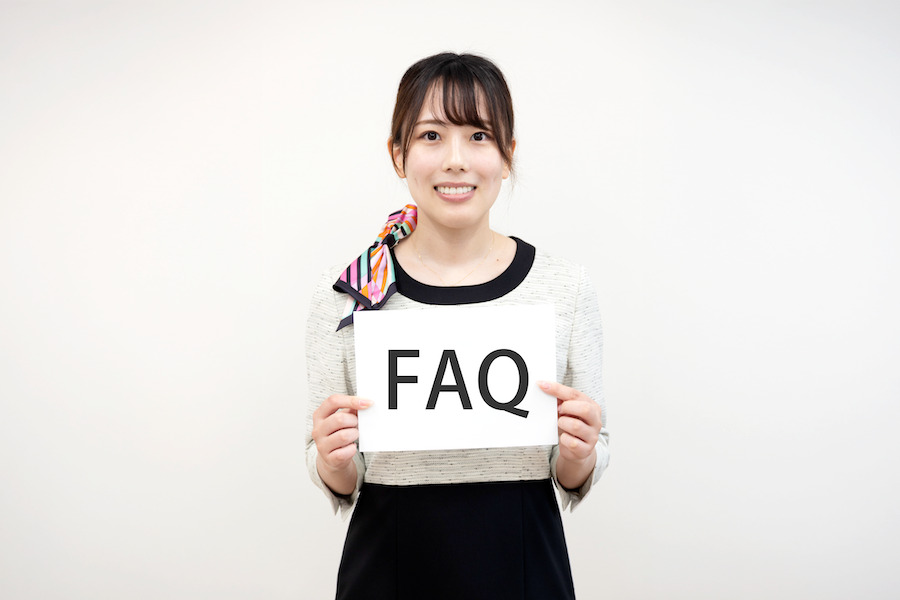
THPと通常の歯周病治療は何が違うのですか?
THPは、歯周病になってから治すのではなく、ならないように整える“予防中心”のプログラムです。
通常の歯周病治療が「症状に対する処置」であるのに対し、THPは細菌や生活習慣の分析を通じて、口腔環境全体を整えることを重視します。
THPを受けるのに痛みや負担はありますか?
THPの検査やプログラムは、基本的に身体的な負担は少なく、痛みを伴う処置はありません。
必要に応じてレーザー治療を行う場合もありますが、痛みや腫れが起きにくく、従来の外科的処置に比べてストレスの少ない内容です。
どのくらいの期間・頻度で通う必要がありますか?
口腔内の状態やリスクレベルによって個人差はありますが、THPは数回の検査とカウンセリングから始まり、継続的なフォローアップを含めておおよそ3か月~半年程度がひとつの目安となります。
定期的な再評価も行います。
保険適用されますか?費用はどのくらいですか?
THPは保険診療の枠を超えた自由診療に該当する部分が多く、検査内容や治療の範囲によって費用が変動します。
詳細な費用については、初回カウンセリング時にご説明しています。
まとめ|“気づいた今”が歯周病対策の第一歩

THP(トータルヘルスプログラム)は、歯周病をただ治療するのではなく、なぜ炎症が起きたのかを明らかにし、再発させないための仕組みまで含めて整える「未来志向の予防医療」です。
出血や腫れといったサインは、口腔内だけでなく、全身の健康状態にも深く関係しています。
THPでは、細菌の状態や生活習慣を多角的に分析し、患者一人ひとりに合わせた予防とケアを継続的に支えていきます。
違和感や不安に気づいた今こそ、歯ぐきの健康を見直す良いタイミングです。