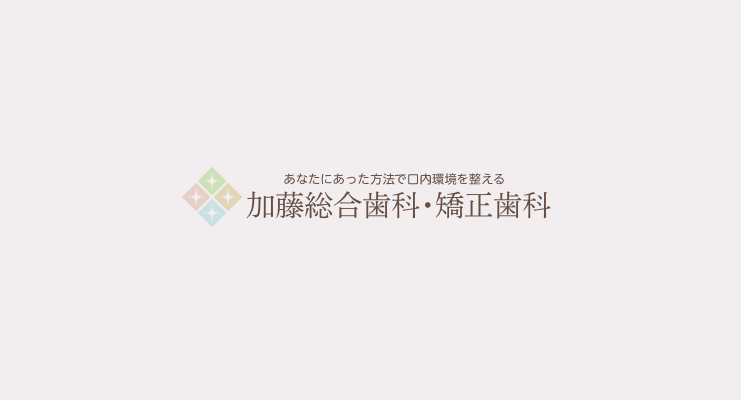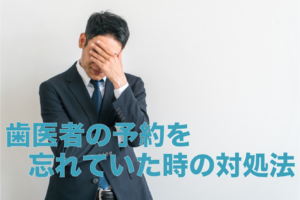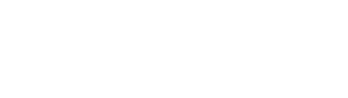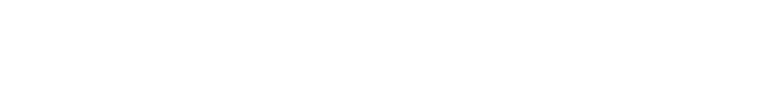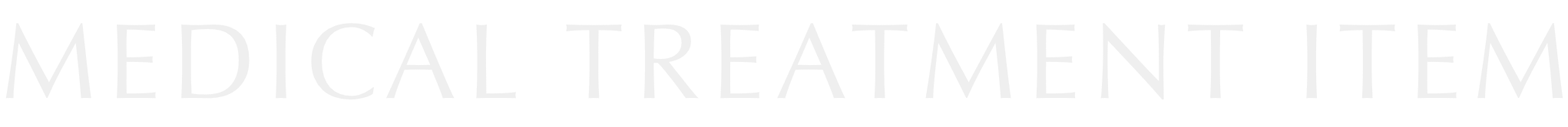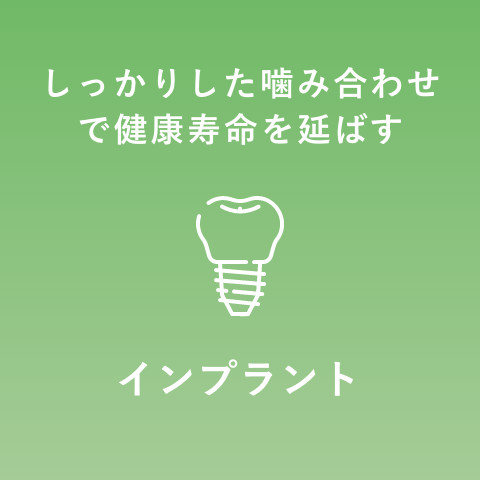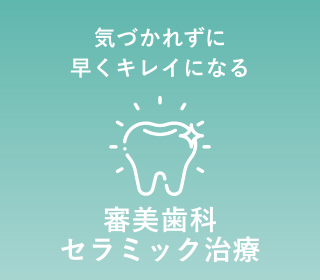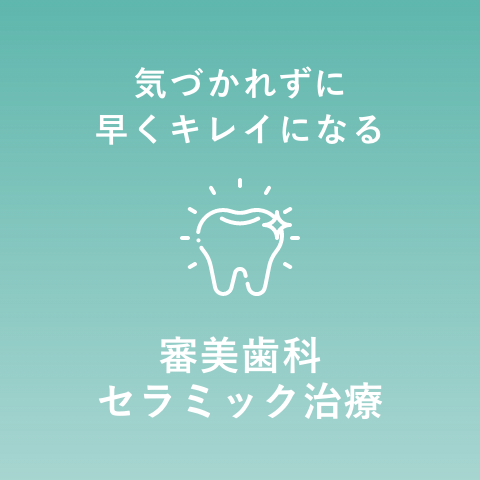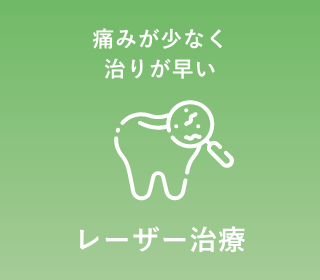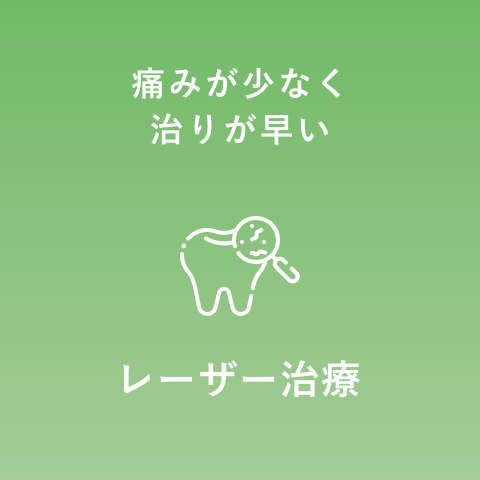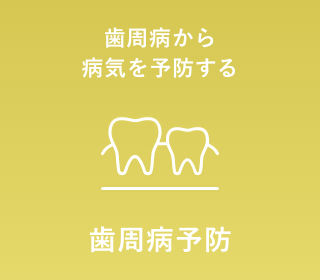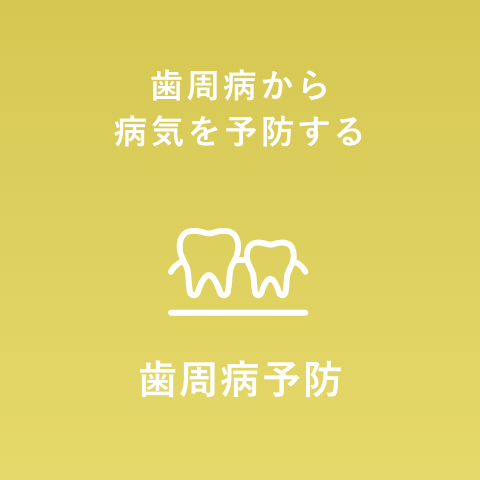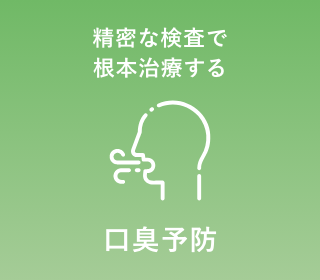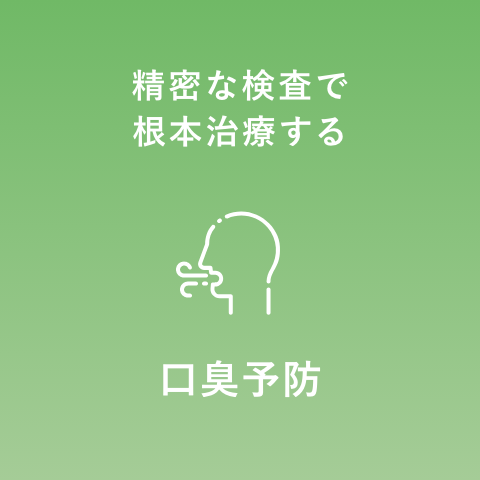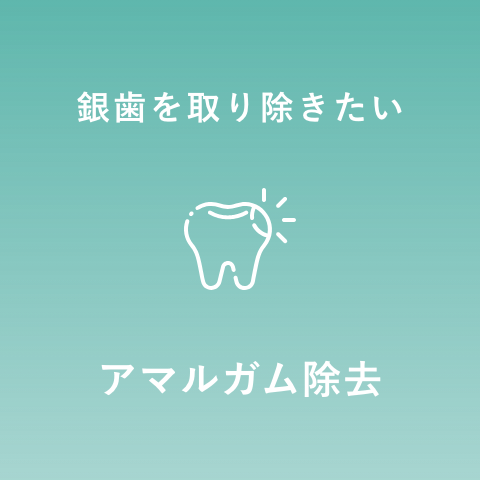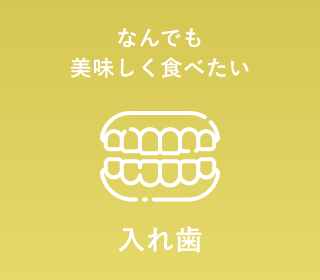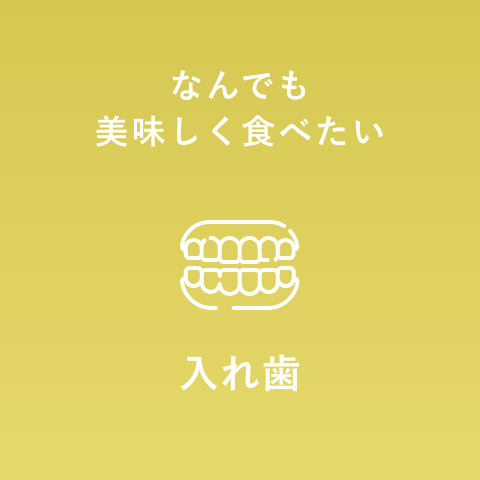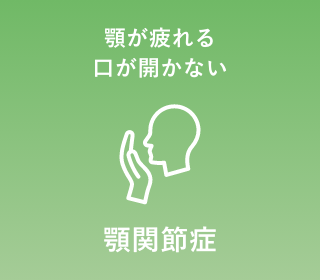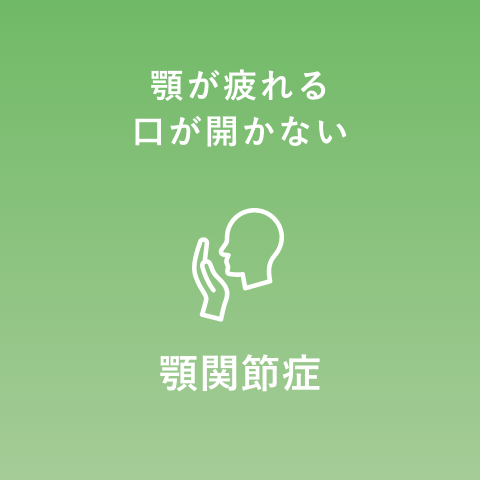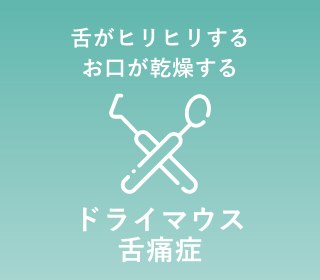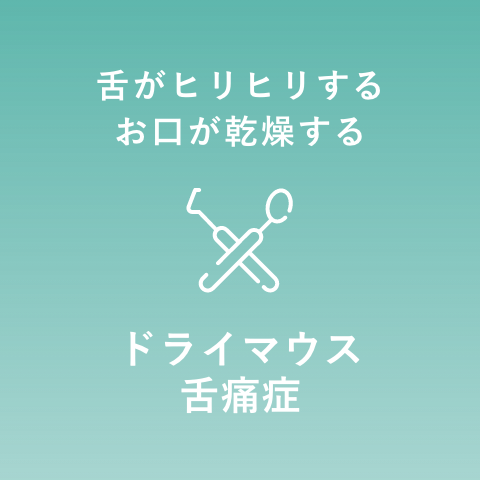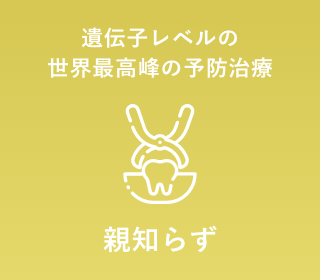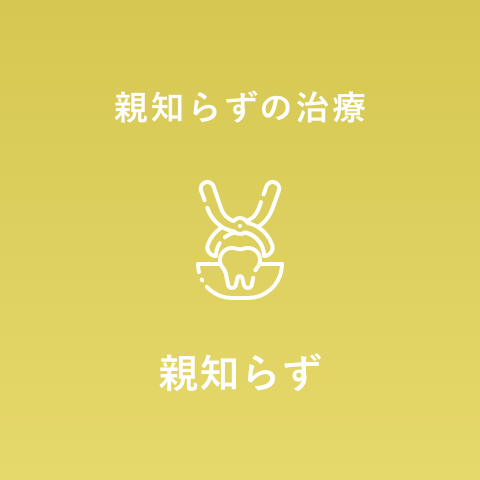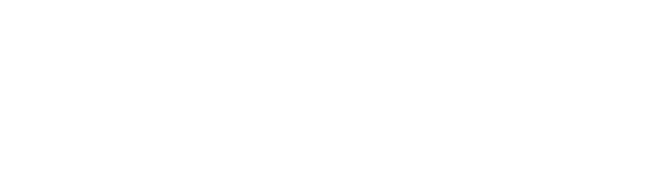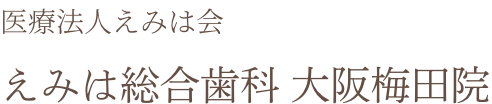口臭の原因が歯周病かもしれないサイン|歯科医が解説する正しい理解と対処法
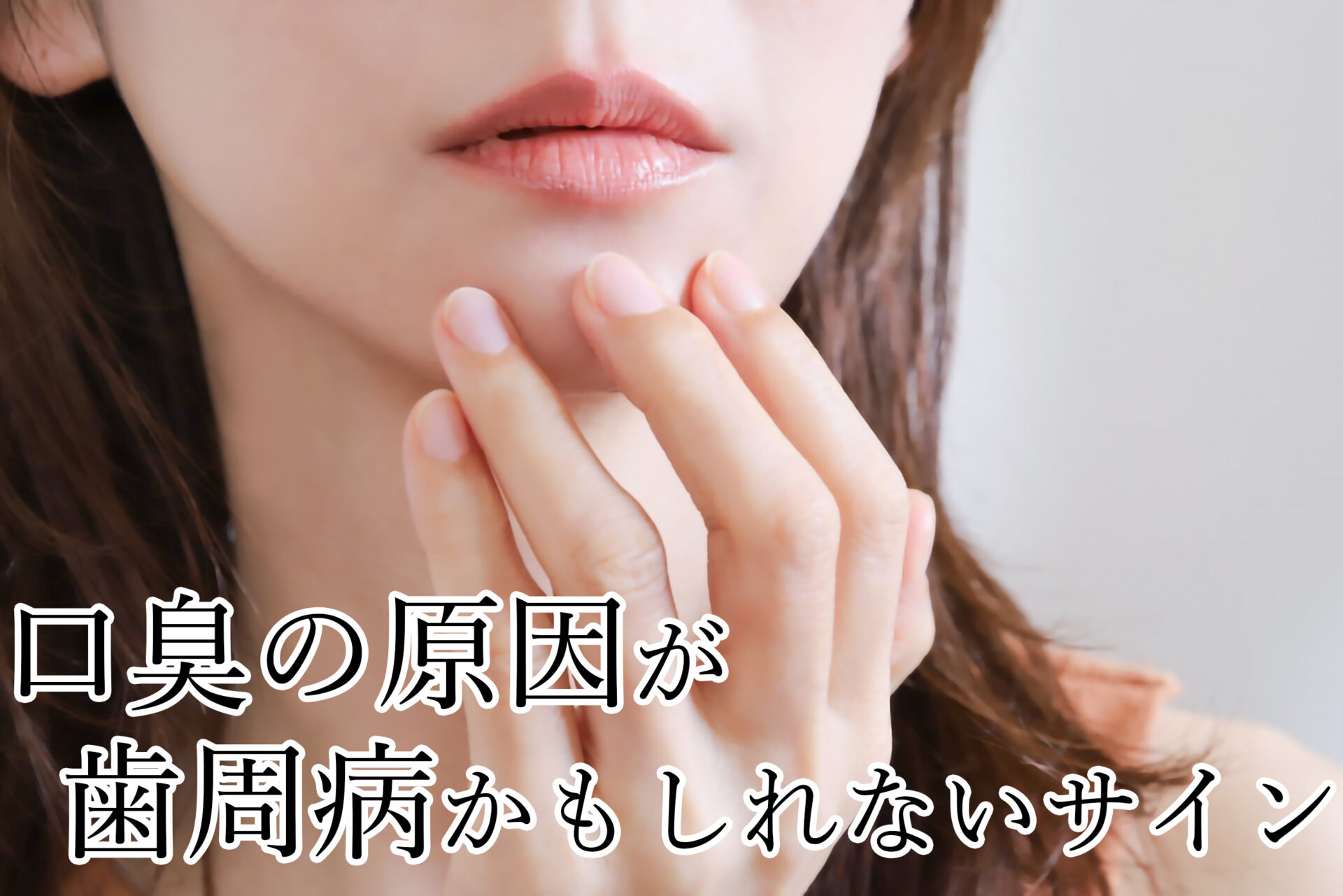
目次
はじめに

「最近、口臭が気になる」「家族や同僚に指摘されて不安」という方は少なくありません。口臭には一時的なものと病気に関連するものがあり、その中でも特に多いのが 歯周病 によるものです。
厚生労働省によると、日本人の成人の約8割が歯周病にかかっていると言われており(【参考文献】eヘルスネット:歯周疾患の有病状況)まさに国民病とも呼ばれる疾患です。本記事では、口臭と歯周病の関係、そして 歯周病を疑うべきサイン を、権威性の高い情報を参照しながら解説します。
1. 口臭の種類と原因

1-1. 生理的な口臭
朝起きたときや空腹時に発生する自然な口臭です。これは唾液の分泌が減少し、口腔内細菌が一時的に増えることによって起こります。
1-2. 食べ物や嗜好品による口臭
ニンニク、アルコール、タバコなどが原因で起こる一時的な口臭です。
1-3. 病的な口臭
口腔疾患や全身疾患に関連する口臭であり、日本口臭学会でも「病的口臭は大きく口腔由来と全身由来に分けられる」と解説されています。
その中でも歯周病は代表的な原因のひとつです。
2. 歯周病と口臭の関係性

2-1. 歯周病とは
歯周病は歯を支える組織に炎症が起こり、進行すると歯槽骨が吸収されて歯が動揺し、最終的には歯を失う可能性のある病気です。
2-2. 歯周病が口臭を引き起こすメカニズム
歯周病菌は、硫化水素やメチルメルカプタンなど揮発性硫黄化合物(VSC)を産生し、強い臭気を発します。この仕組みについては歯科医療の現場からも信頼される製品を開発している、信頼性の高いオーラルケアブランド「システマ」でも解説されています。
(【参考文献】システマ:歯周病と口臭)
2-3. 歯周病による口臭の特徴
- ガムや歯磨きで一時的に改善してもすぐ戻る
- 他人が気づきやすい強い臭い
- 歯ぐきの出血や腫れを伴うことが多い
3. 歯周病かもしれないサイン

厚労省 e-ヘルスネットによると、歯周病の初期症状として「歯ぐきからの出血・腫れ」が挙げられています。
(【参考文献】厚生労働省e-ヘルスネット:歯周疾患の自覚症状とセルフチェック)
以下のサインがあれば注意が必要です。
- 歯ぐきから出血する(ブラッシングやフロス使用時)
- 歯ぐきが赤く腫れている
- 歯が揺れるように感じる
- 口の中がネバつく
4. 歯科医院で行う口臭・歯周病の検査

歯科医院では以下の検査が行われます。
- 歯周ポケット測定:歯周病の進行度を把握
- レントゲン検査:骨の吸収具合を確認
- 口臭測定器:揮発性硫黄化合物の濃度を測定
5. 歯周病治療の一般的な流れ

5-1. スケーリング(歯石除去)
歯石を除去し、細菌の温床を取り除きます。
5-2. SRP(ルートプレーニング)
歯周ポケット内部を清掃し、歯根表面をなめらかに整えます。
5-3. 外科治療(必要な場合)
重度歯周病では歯ぐきを開いて深部の歯石や感染組織を除去する場合もあります。
5-4. メンテナンス
治療後は定期的なクリーニングが不可欠であり、厚労省も「定期的な歯科受診が歯周病の進行予防に有効」と述べています
(【参考文献】歯の健康|厚生労働省】)
6. 自宅でできる歯周病予防と口臭対策

- 正しいブラッシング:歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨く
- フロス・歯間ブラシ:歯間のプラーク除去
- 舌清掃:舌苔は日本口腔外科学会でも口臭の原因として強調されています
(【参考文献】日本口腔外科学会:口臭がひどい|口腔内のトラブル)
食生活改善:野菜や咀嚼回数の多い食事は自然な清掃効果あり
7. 歯周病治療のメリットとリスク

歯周病治療を検討する際には、そのメリットとリスクを正しく理解することが重要です。治療により得られる効果と、起こりうる副作用について詳しく解説します。
メリット
口臭の改善が期待できる
なぜ歯周病治療で口臭が改善するのか
歯周病による口臭の主な原因は、歯周病菌が産生する揮発性硫黄化合物(VSC)です。特にメチルメルカプタンや硫化水素といった物質が、特有の不快な臭いを発生させます。
治療による改善メカニズム
- 歯石除去により細菌の住処を取り除く
- 深い歯周ポケットの清掃で嫌気性菌を減少させる
- 炎症の改善により組織の腐敗臭が軽減される
- 唾液の流れが改善し、自浄作用が回復する
歯ぐきの健康回復
炎症の軽減による見た目の変化
歯周病治療により、歯ぐきの炎症が改善すると以下のような変化が現れます。
- 色の変化:赤く腫れた歯ぐきが健康なピンク色に戻る
- 形状の回復:ぶよぶよと腫れていた歯ぐきが引き締まる
- 出血の停止:歯磨き時の出血が徐々に減少し、最終的に止まる
- 痛みの軽減:歯ぐきを触った時の痛みや違和感が改善
歯ぐきの機能回復
治療により、以下の機能回復が見込めます。
- バリア機能の復活:細菌の侵入を防ぐ防御壁としての役割
- 栄養供給の改善:血流が回復し、歯を支える組織への栄養供給が正常化
- 再生能力の向上:軽度な損傷に対する自己修復能力が回復
全身疾患(糖尿病・心疾患など)のリスク軽減にもつながる可能性がある
糖尿病との相互関係改善
歯周病治療が糖尿病に与える影響について、日本歯周病学会より以下のような結果が報告されています。
- 血糖値の改善:歯周病治療後、HbA1c(過去2〜3ヶ月の血糖値の平均)が0.4〜0.7%改善したという報告
- インスリン抵抗性の軽減:慢性炎症の改善により、インスリンの効きが良くなる
- 薬物治療の効果向上:歯周病治療により糖尿病薬の効果が高まる場合がある
(【参考文献】日本歯周病学会:歯周病治療ガイドライン)
心血管疾患リスクの軽減
歯周病治療により、心血管疾患リスクを軽減できます。
- 全身炎症の軽減:C反応性蛋白(CRP)などの炎症マーカーの改善
- 動脈硬化進行の抑制:血管内皮機能の改善
- 血栓形成リスクの低下:血液凝固能の正常化
- 血圧への好影響:慢性炎症の改善による血圧安定化
その他の全身疾患への影響
- 認知症予防:脳への慢性炎症の影響を軽減する可能性
- 関節リウマチ:炎症性サイトカインの減少により症状改善の可能性
- 妊娠への影響:早産や低体重児出産のリスク軽減
リスク
治療後に一時的な知覚過敏
知覚過敏が起こる理由
歯周病治療後の知覚過敏は、以下のメカニズムで発生します
- 歯根面の露出:歯石除去により、今まで覆われていた歯根面が露出
- 象牙細管の開口:歯根面にある微細な管(象牙細管)が外部に露出
- 神経への刺激伝達:冷たい物や甘い物の刺激が神経に直接伝わる
知覚過敏の特徴と経過
- 症状の現れ方:冷たい飲み物や風にしみる、甘い物で痛む
- 持続期間:通常1〜4週間程度で自然に改善
- 個人差:歯根の露出程度や個人の感受性により差がある
- 改善過程:歯根面に新たな組織が形成され、徐々に症状が軽減
対処法
- 知覚過敏用歯磨き粉の使用
- フッ素塗布による歯質強化
- 必要に応じてコーティング材の使用
出血を伴う場合がある
治療直後の出血について
歯周病治療後の出血は、以下の理由で起こります
- 炎症組織の除去:感染した組織を除去する際の一時的な出血
- 血流の改善:治療により血流が改善し、一時的に出血しやすくなる
- 組織の修復過程:傷ついた組織が治癒する過程での自然な反応
出血の経過と対処
- 持続期間:通常24〜48時間で自然に止まる
- 正常な反応:軽度の出血は治癒過程の正常な反応
- 注意が必要な場合:大量の出血や長期間続く場合は医師に相談
まとめ

口臭の原因にはさまざまなものがありますが、歯周病は最も多い原因のひとつ です。歯ぐきからの出血や腫れ、歯の動揺、口のネバつきが見られる場合は、早めの受診をおすすめします。
歯周病治療は口臭改善だけでなく、歯の寿命や全身の健康にもつながります。気になるサインがある方は、一度歯科医院で検査を受けましょう。