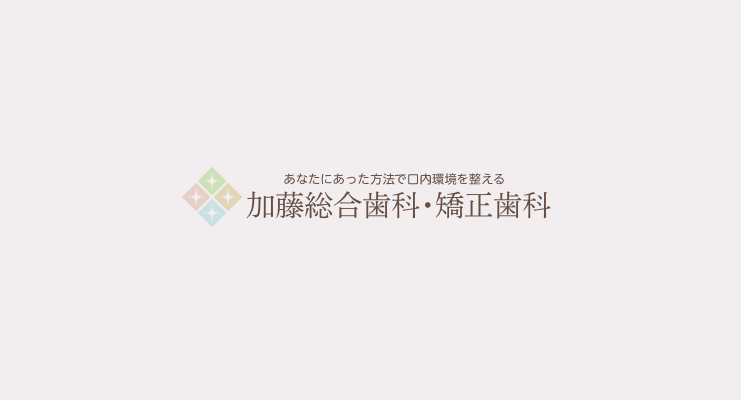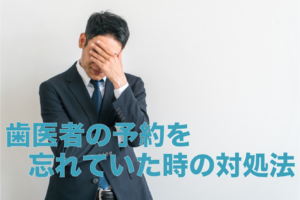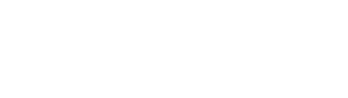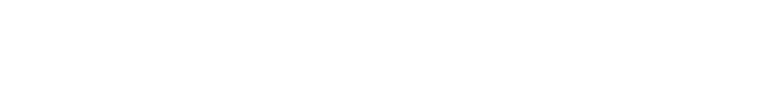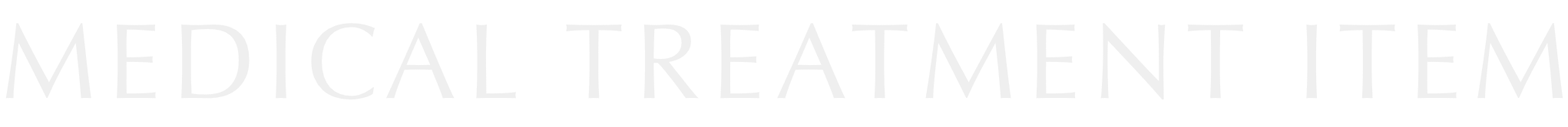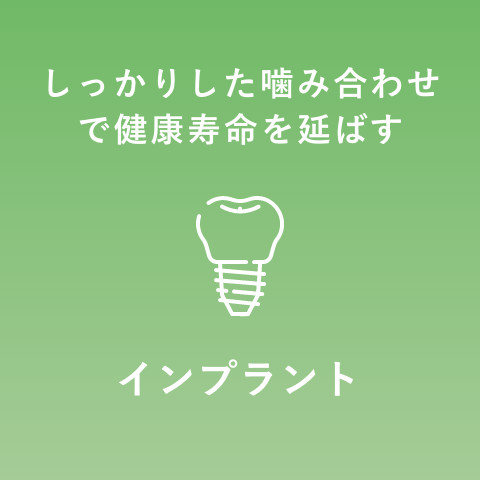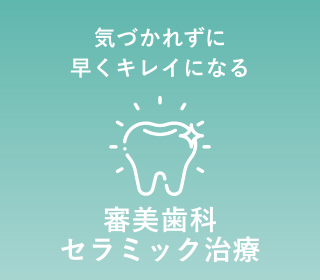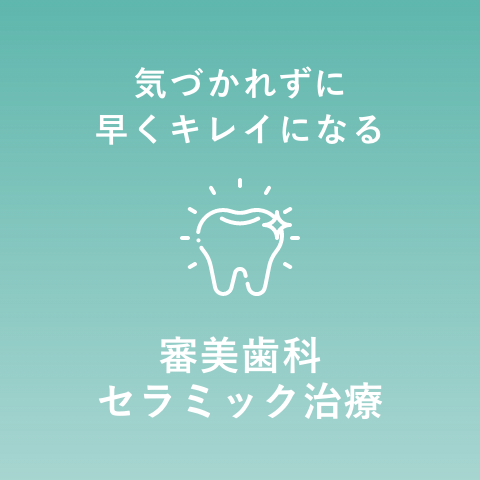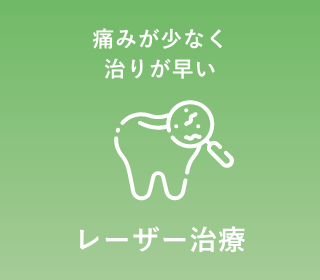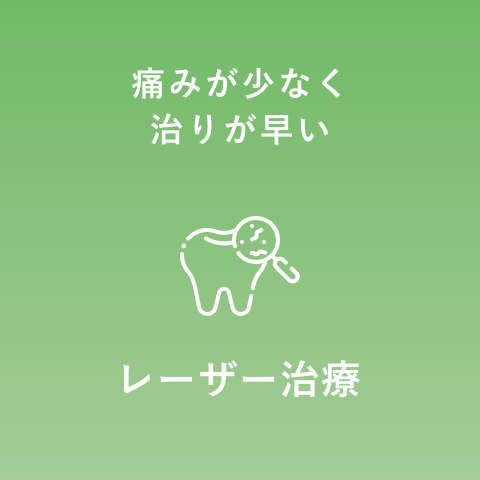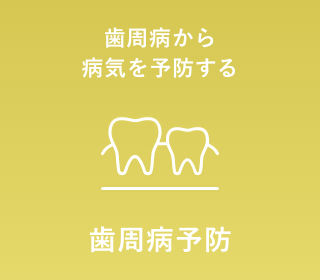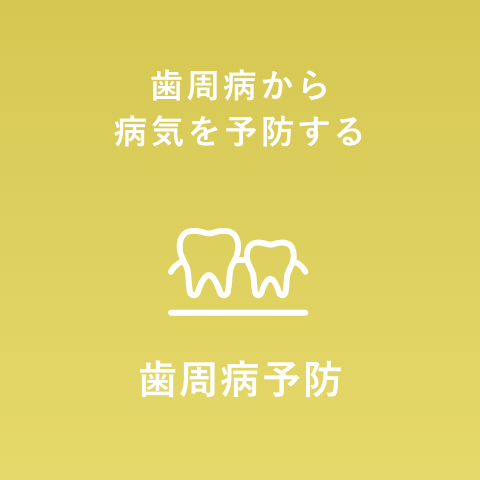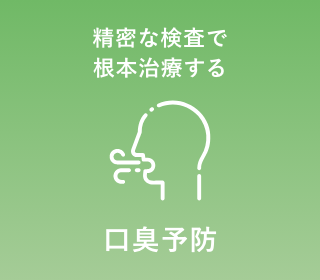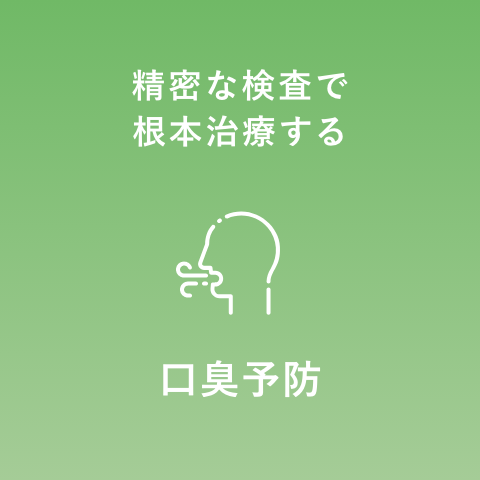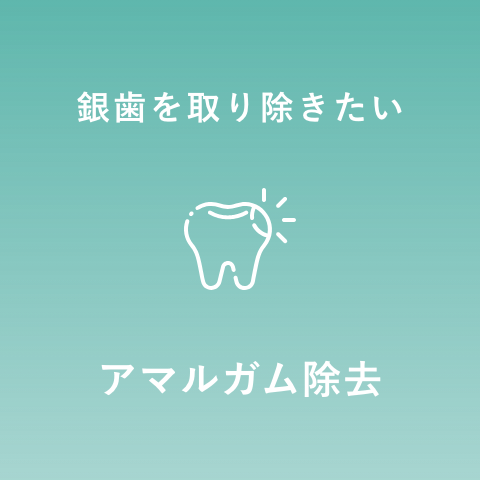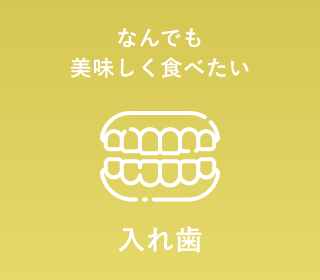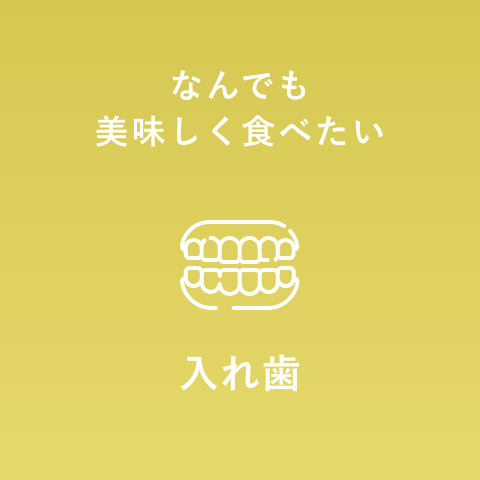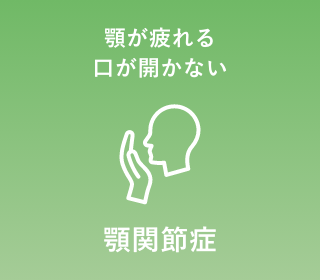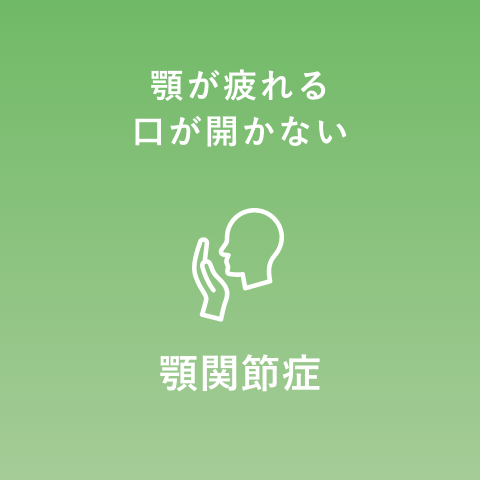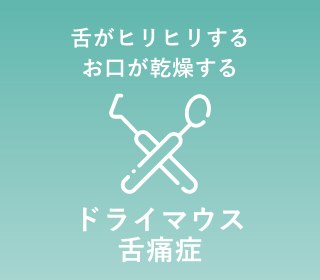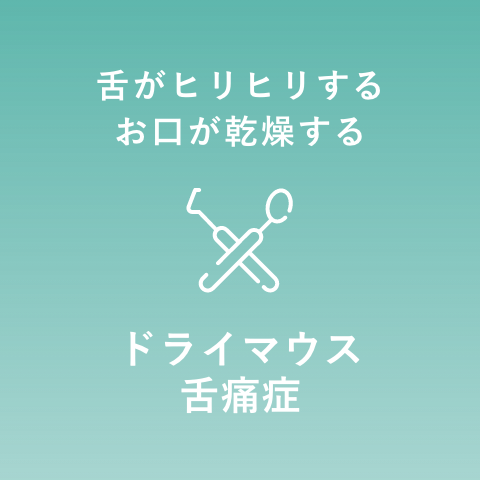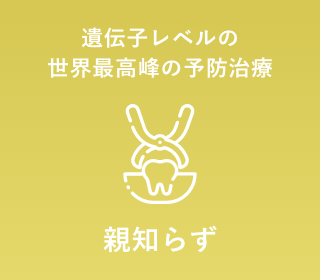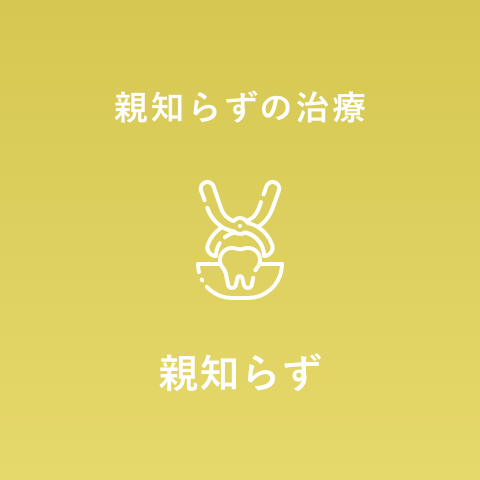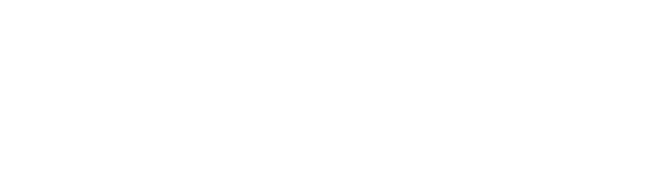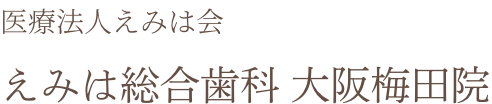歯周病の原因は?悪化させる5つのリスクファクターと進行度別の治療方法

こんにちは!大阪 梅田のえみは総合歯科、理事長の加藤直之です。
歯磨きの際に出血や歯茎の違和感などを覚え、歯周病ではないかと不安視する方もいるでしょう。
歯周病は歯垢(プラーク)に潜む歯周病菌が原因で起こる感染症で、自覚症状が乏しいまま進行します。また、気づいたときには歯がグラつき、抜けてしまうことも少なくありません。
本記事では、歯周病の原因と悪化させるリスクファクターについて解説します。進行度別の治療方法や予防法も紹介するので、参考になれば幸いです。
当院では、保険適用で行う歯周病治療だけでなく、虫歯や歯周病にかかりにくくする根本的歯周病治療を取り入れております。
目次
歯周病の直接的な原因とは?

歯周病の直接的な原因は歯垢(プラーク)で、歯垢に潜む細菌の感染により歯の周りの歯茎や骨が壊されます。
歯垢は生きた細菌の塊で、歯茎に炎症を起こす毒素を出します。適切なブラッシングで除去しないと時間とともに歯石へと再石灰化し、自分では取り除けません。
軽度の症状には歯茎の腫れや出血が挙げられますが、自覚症状を感じない方もいるでしょう。
しかし、さらに進行すると排膿や歯の動揺を起こし、最終的には抜歯が必要になってしまうケースもあります。
歯周病の間接的な原因5選

歯周病の直接的な原因は歯垢ですが、口腔内の環境や生活習慣などのなかには歯周病を悪化させる間接的な原因が潜んでいます。
間接的な原因である「リスクファクター」は以下の5つです。
- 歯石
- 歯並び
- 合っていない被せ物
- 歯ぎしり・食いしばり
- 生活習慣
それぞれ解説するので、参考にしてください。
歯石
磨き残した歯垢に唾液中のカルシウムが作用して石灰化した歯石は、歯磨きでは落とせません。
歯石の表面には細菌が存在し、ザラザラしているため歯垢がより付着しやすくなります。さらに、歯石が増えることで口腔内の細菌が増加し、毒素を量産するため歯周病が悪化してしまいます。
歯石は歯科医院で専用の器具を使って落とす必要がありますが、柔らかい歯垢ならブラッシングで落とすことが可能です。
丁寧な歯磨きを心がけ、歯石になるのを予防しましょう。
歯並び
歯並びが悪い部分は歯磨きが行き届かず、歯垢が溜まりやすいため、歯周病が悪化しやすくなります。
例えば、歯が重なり合う叢生では歯と歯の間の歯磨きが難しく、磨き残ししやすい歯並びです。
歯並びが悪い人は並びの良い人と比べて、歯周病だけでなく虫歯のリスクも高くなります。また、歯並びの悪い部分だけでなく、隣接する歯も影響を受けてしまうでしょう。
歯周病を予防するためには、歯科医院で定期検診を受け、口腔内の状態をチェックしてもらうことをおすすめします。歯並びが悪い場合は、矯正治療などで改善することを検討しましょう。
合っていない被せ物
合っていない被せ物は歯との隙間に歯垢が溜まり、歯周病が進行しやすくなります。
被せ物は虫歯の治療などのために歯を削り、削った部分を補うための処置です。
例えば、被せ物と土台となる歯の間に隙間が生じると歯垢が溜まり、歯ブラシでは落としにくくなります。また、被せ物の噛み合わせが悪いと、特定の歯に負担が偏ってしまいます。
そのため、続けて使っていると周辺の骨が吸収してしまい、歯周病が進行しやすくなることも少なくありません。
歯科医院で定期検診を受け、被せ物の状態をチェックしてもらいましょう。合っていない被せ物は、作り直しや調整することで改善可能です。
歯ぎしり・食いしばり
睡眠中に強く噛み合わせる歯ぎしりや食いしばりは、長時間続くことで歯を支える骨を吸収させてしまいます。
自覚症状がない場合が多く、放置すると歯周病を悪化させるリスクを高めます。
食事で噛み合わせる時間は1日に20分程度である一方、歯ぎしりや食いしばりは一晩中続くこともあり、その差は歴然です。
長時間噛み合わせの力を強く受けると歯を支える骨が吸収し、歯が動揺します。さらに放置して症状が進むと、最終的には抜歯になるケースがあるのも事実です。
歯ぎしり・食いしばりは歯周病だけでなく、歯や顎関節にも悪影響を及ぼします。自覚症状がない場合でも、定期検診などでチェックしてもらいましょう。
生活習慣
日常的に行われる生活習慣にも、歯周病を悪化させる原因は潜んでいます。歯周病に影響を及ぼす生活習慣は、以下のとおりです。
- 喫煙
- ストレス
- 食生活
喫煙はタバコに含まれるニコチンが血管収縮を引き起こし、歯茎の血行不良を起こします。血行不良を起こした歯茎や周辺の組織は栄養不足になり、歯周病菌への抵抗力が低下し歯周病が進行しやすいと言われています。
また、精神的ストレスは歯周病菌への抵抗力を弱めるだけでなく、生活習慣の変化を引き起こすことも少なくありません。特に、食生活や歯磨き習慣、喫煙などの生活習慣は変化しやすいため、ストレスの影響を受けやすいでしょう。
ほかにも、不規則な食生活や栄養バランスの悪い食事は、体だけでなく歯茎にも影響を及ぼします。例えば、甘いものや柔らかいものは歯の表面につきやすく、歯垢を増やす原因となるため注意してください。
歯周病の治し方は?4段階の進行過程と症状
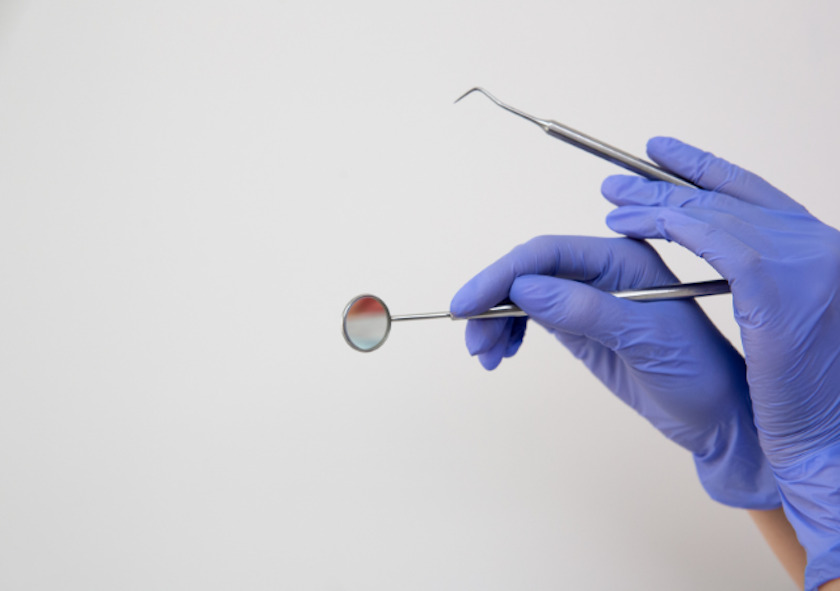
歯周病の治し方を進行度別に、以下の表にまとめました。
健康な歯茎は薄いピンク色で引き締まっています。また、歯磨きの際の出血もほぼ見られず、1〜2mmの歯肉溝が見られます。
歯周病は大きく分けて、歯茎だけに炎症が起きる歯肉炎と周辺組織に炎症が起こる歯周病の2つです。なかでも、歯周炎は進行度別に3つに分けられます。
また、歯周病の治し方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
関連記事:歯槽膿漏の7つの治し方とは?自宅でできる予防法や治療薬の効果も解説
歯肉炎
歯肉炎は歯と歯茎の境に歯垢が溜まったことで炎症が起こり、2〜3mmの歯周ポケットが形成された状態です。
症状には、歯茎の腫れや歯磨きの際に起こる出血が挙げられます。
治療として、歯垢が取れるようにするためのブラッシング指導や、スケーリングを行います。
歯肉炎の炎症は歯茎に留まっているため、適切な治療で完全に治癒することが可能です。
症状の一つである歯茎の腫れに関しては、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:歯茎が腫れる原因は?自分でできる応急処置と治し方を徹底解説
軽度の歯周病
軽度の歯周病は歯肉炎が進行し、歯を支えている歯周組織の破壊が始まった状態です。
歯周ポケットは3〜5mmと深くなり、症状には歯茎の腫れや出血、歯茎が下がることなどが挙げられます。
治療はブラッシング指導やスケーリング、歯周ポケット内の歯垢や歯石を専用の器具で除去するSRPを行うのが一般的です。
軽度の歯周病は、適切な治療と丁寧なセルフケアで症状の改善と進行予防が可能です。
歯茎が下がる症状に関してはこちらの記事で詳しく紹介しているので、合わせてご覧ください。
関連記事:歯茎が下がるのはどうして?原因と効果的な5つの予防法を解説
中等度の歯周病
中等度の歯周病はさらに進行し、歯槽骨が半分くらい吸収された状態です。
歯周ポケットは4〜7mm程度とさらに深くなり、症状には口臭の悪化や排膿、歯の動揺が挙げられます。
治療は軽度歯周病と同様に、ブラッシング指導やスケーリング・SRPを行います。ただし、歯周ポケットが深い分ポケット内の歯垢や歯石の量が増え、SRP1回あたりの時間や回数が増えるでしょう。
中等度の歯周病は適切な治療で症状の改善と進行の阻止は可能ですが、失われた歯周組織は元に戻りません。
したがって、軽度の段階からの早期発見・早期治療、丁寧なセルフケアが重要です。
重度の歯周病
重度の歯周病では歯槽骨が半分以上溶かされ、歯はグラグラと動揺している状態です。
歯周ポケットは6〜7mm以上で、症状には膿が溜まって大きく腫れる・痛みを伴う・食事に支障が出るなどが挙げられます。さらに、放置すると自然に抜け落ちることも珍しくありません。
治療はブラッシング指導やスケーリング・SRPを行い、必要に応じて歯周外科処置を行います。歯周外科処置は汚染された歯茎の切除や、SRPで取りきれない歯垢・歯石の除去を行う治療方法です。
歯周病の進行が著しく周囲に悪影響を与える場合は、無理に残さずに抜歯するケースがあるのも事実です。
重度の歯周病では、歯を失うリスクが大幅に高まります。早期発見・早期治療が重要ですが、失われた歯周組織は元に戻せないため、予防が最も重要です。
歯周病の予防方法3選

歯周病は治療もできますが、予防することも可能です。
予防方法として効果的なのは、以下3つです。
- 丁寧な歯磨き
- 生活習慣の改善
- 定期検診
歯周病の予防には直接的な原因である歯垢をためないことや、間接的な原因を改善することが大切ですので、参考にしてください。
丁寧な歯磨き
歯周病予防には、毎日の丁寧な歯磨きが欠かせません。歯垢を徹底的に除去し、歯周病菌の増殖を抑えると、歯周病の発症・悪化を予防できます。
丁寧な歯磨きのコツとして、以下を参考にしてください。
- バス法
- 定期的な歯ブラシの交換
- 補助用具の使用
バス法は、歯垢が溜まりやすい歯と歯茎の境に毛先を45度に当て、1〜2本を磨くように小刻みに動かす歯磨き方法です。動かす際には、ブラッシング圧が強くならないように注意しましょう。
また、使用する歯ブラシは使いやすいもので構いませんが、1ヶ月を目安に交換してください。毛先が開いていたり、長期間使っていたりする歯ブラシは汚れが落ちにくくなります。
ほかにも、歯ブラシだけで取りきれない歯垢は、歯間ブラシ・フロス・ワンタフトブラシなどの補助用具を併用するのがおすすめです。
生活習慣の改善
歯周病の予防には歯磨きだけでなく生活習慣を改善すると、歯周病リスクをさらに減らせます。
改善をおすすめする生活習慣は、以下のとおりです。
- 喫煙
- ストレス
- 食生活
なかでも、喫煙は歯周病を悪化させるうえ、治療の効果も妨げます。口腔内だけでなく、全身の健康のためにも禁煙がおすすめです。
ストレスはできるだけ持ち越さないように、自分に合った気分転換をしましょう。
食生活では栄養バランスの取れた食事で免疫力アップを心がけてください。
特に、歯垢の元となる糖分の多い食品やだらだら食いは控え、歯周組織の抵抗力をつける栄養分であるタンパク質・カルシウム・鉄分・ビタミンAやCの摂取がおすすめです。
定期検診
定期検診は歯周病の予防だけでなく、早期発見・早期治療のために最も重要です。
歯周病は軽度ではほとんど症状がなく、自覚症状のないまま進行するため自分ではなかなか気づけません。症状が出たときには重度の歯周病に進行することもあります。
特に、歯石がついてしまうと歯磨きでは取れないため、定期的なスケーリングがおすすめです。
少なくとも半年ごとに年2回は歯科医院で専門的な検査やケアを受け、健康な口腔内を守りましょう。
歯周病は病気の原因になる?起こりうる4つの全身への影響

歯周病の炎症によって出る毒性物質が歯茎の血管から全身に入ると、さまざまな病気を引き起こしたり悪化させたりする原因となります。
起こりうる全身への影響は、以下4つです。
- 糖尿病
- 誤嚥性肺炎
- 心疾患・脳血管疾患
- 早産・低体重児出産
歯周病は口腔内の病気だからと軽視せず、参考にしてください。
糖尿病
以前から「歯周病は糖尿病の合併症の一つ」と言われるほど、互いに悪影響を与えます。
実際に、糖尿病の人は健康な人と比べて歯肉炎・歯周病にかかっている人が多いと言われています。また、歯周病になると、糖尿病の症状が悪化するケースがあるのも事実です。
すでに糖尿病を患っている場合は、歯周病になりやすく重症化しやすい傾向があるため、特に注意が必要です。
健康状態に問題がなくても、毎日の食生活を見直し歯周病を予防することが、糖尿病やほかの生活習慣病の予防に繋がるでしょう。
誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液に含まれる口腔内の細菌を誤って気管や肺に飲み込んでしまうことで発症する肺炎です。
本来、肺や気管は咳をすることで異物が入らないように守りますが、高齢になると歯周病菌を含む口腔内の細菌を誤嚥しやすく誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
誤嚥性肺炎の原因菌は歯周病菌が多いと言われており、重症化させる可能性があります。
特に、免疫力の衰えた高齢者に多いと言われているため、誤嚥性肺炎予防のためにも歯周病のコントロールが重要です。
心疾患・脳血管疾患
不適切な食生活や運動不足などの生活習慣が原因とされる動脈硬化は、ほかの原因として歯周病菌が注目されています。
歯周病菌が血管に入り込み炎症を引き起こすと血栓ができやすく、血管を詰まらせます。
心疾患や脳血管疾患は動脈硬化や血管の詰まりによって引き起こされることがほとんどです。
特に血圧・コレステロール・中性脂肪が高めの方は注意が必要です。心疾患・脳血管疾患を予防するためにも、歯周病の治療と予防に努めましょう。
早産・低体重児出産
妊娠中の女性が歯周病に罹患していると、早産や低体重児出産のリスクが高まると言われています。
歯周病菌が血液中から胎盤を通して胎児に感染すると言われており、歯周病による危険率はタバコやアルコール・高齢出産に比べて7倍ほど高い傾向にあります。
一般的に、妊娠すると女性ホルモンの影響で歯肉炎になりやすいため、胎児の成長に影響を及ぼさないためにも注意しましょう。
産後も親から子へ歯周病菌が感染しないように歯磨きを丁寧にすることや、自家箸で食べさせないように気をつけてください。
歯周病の感染については、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:歯周病はうつるのか?5つの感染経路や発症を予防するための対策も紹介
歯周病の原因でよくある質問

歯周病の原因に関してよくある質問を、以下にまとめました。
- 歯周病における手遅れな症状は?
- 歯周病になりやすい人はどのような人か?
詳しく解説するので、参考にしてください。
歯周病における手遅れな症状はどのようなものですか?
歯周病において手遅れな症状は、以下のとおりです。
- 歯が動いて噛みにくい
- 歯が上下に動く
- 噛むと痛い
噛む際に力が入らない場合、歯が上下に動揺しているため噛むと歯が沈んでしまいます。
軽度〜中等度の歯周病では前後左右に動揺しますが、重度の場合は歯槽骨の吸収が大きく上下に動揺するのが特徴です。
状態によっては、噛む際に痛みを伴うこともあるでしょう。周囲に影響を及ぼす場合は、無理に残さず抜歯することも珍しくありません。
歯周病になりやすい人はどのような人ですか?
歯周病になりやすい人は、以下のとおりです。
- 歯磨きが不十分
- 歯並びが悪い
- 喫煙する
- 口呼吸である
- 歯ぎしりの習慣がある
- 糖尿病である
- 降圧剤・抗てんかん薬・免疫抑制剤などを服用している
歯磨きが不十分な人や歯並びが悪い人は、歯周病の直接的な原因である歯垢が残ってしまうため、歯周病になりやすいでしょう。
喫煙による血行不良や、口呼吸が原因で起こる口腔内の乾燥により自浄作用が望めないと歯周病菌が増殖しやすくなります。
また、歯ぎしりの強い力は歯や歯槽骨に負担がかかり、歯周病が進行しやすくなります。
ほかにも、歯周病になりやすいとされる全身疾患もあり、糖尿病は影響を受けやすい疾患の一つです。
服薬の影響を受けやすい薬剤には降圧剤・抗てんかん薬・免疫抑制剤などが挙げられます。なかでも、降圧剤は副作用で歯茎が腫れることがあるため、服薬していない方と比べると歯周病になりやすいと言えるでしょう。
まとめ|歯周病で手遅れにならないよう早めに受診しよう

歯周病の直接的な原因は歯垢ですが、間接的な原因が関与することでさらに進行してしまいます。
歯周病は治療できる病気であり、予防もできます。歯周病予防のためには、歯科医院での治療や定期検診だけでなく自宅での丁寧なセルフケアが欠かせません。
また、症状がないからと安心していると自覚症状がないまま進行するため、定期検診でのチェックが大切です。
全身疾患へと影響を及ぼす可能性もあるため、少しでも思い当たる症状があれば早めに受診しましょう。
当院では、初診時にカウンセリングや検査を行い、患者さんに合わせた治療方針を説明します。不安な点などありましたら、お気軽にご相談ください。